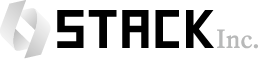生成AIは、文章の作成やアイデア出しなど、私たちの仕事を支える強力なツールとして注目されています。
しかし一方で、「なんでもできる魔法の技術」と誤解されることも少なくありません。
実際のところ、AIには得意な領域と苦手な領域がはっきり存在します。この記事では、その違いを具体的に整理しながら、AIを正しく活用するための視点を解説します。
1. 生成AIが得意なこと
ここでは、生成AIが特に得意とする3つの分野を見ていきましょう。生成AI(Generative AI)は、近年もっとも注目を集めているテクノロジーのひとつです。人間のように文章を書いたり、画像を作ったり、アイデアを出したりする能力を備え、私たちの業務や生活を大きく変えつつあります。
1-1. パターン認識と自然な文章生成
生成AIの最大の強みは、AIは膨大なテキストデータを文体や語順、表現の傾向などから学習し、人間が書いたような自然な文を短時間で生成できる点です。AIは、「意味を理解している」ことではなく、過去に学習した膨大な文章パターンの中から最も自然に続く言葉を確率的に導き出す点にあります。つまり、生成AIは「正しい言葉の並び」を導くのが得意なのです。
生成AIの活用場面
- 文体の調整:トーンを指定するだけで、自然かつ読みやすい文を生成する。
- メール文の作成:ビジネスメールやお礼文などを整える。
- 記事の下書き:構成や流れを自動的に組み立てる。
- 商品の紹介文:特徴や魅力を自然なトーンで文章化する。
1-2. 情報整理とアイデアの拡張
生成AIは、複数の情報を結びつけて整理するのも得意です。たとえば「SNSマーケティングの成功事例を踏まえた新しいキャンペーン案を考えて」といった質問に対して、関連する要素を自動で抽出し、論理的に整理された提案を返すことができます。
生成AIの活用場面
- 企画書や提案書のたたき台づくり:構成や内容を素早く整え、検討の出発点を作る。
- 過去の事例やトレンドの組み合わせ:既存の知識をつなぎ合わせて、新しい切り口やアイデアを提示。
- 大量情報の横断的整理:異なる分野のデータを比較し、関連性を見出す。
- ブレーンストーミングの補助:発想を広げたいときに多角的な視点を提案。
1-3. 翻訳・要約・質問応答の正確性
文章の要約や翻訳、質問応答など、情報を再構成するタスクはAIの得意領域です。たとえば、英語のニュース記事を自然な日本語に翻訳したり、長いレポートを数行で要約したりする作業を、わずか数秒で完了できます。ChatGPTのような生成AIは、単なる翻訳だけでなく、文体やトーンの調整なども行えます。
生成AIの活用場面
- 翻訳:英語・中国語など多言語の記事や資料を、自然な日本語に変換。
- 要約:長文のレポートや議事録を、要点だけにまとめて短縮。
- 質問応答:過去の情報や文脈から、最も関連性の高い答えを提示。
2. 生成AIができないこと
生成AIは「人間のように考える」わけではありません。AIの出力は、あくまで過去のデータを再構成した結果に過ぎず、その中には人間が本能的に行っている「理解」や「判断」が欠けています。ここでは、AIの限界を3つの側面から整理します。
2-1. 言葉の意味を理解すること
厳密に言うと、生成AIは人間が使う言葉の意味を理解しているわけではありません。あくまで、過去の膨大なデータを学習し、「この単語の次にどの言葉が自然か」を確率的に導き出しているだけです。
たとえば、「太陽が沈むとどうなる?」と尋ねると、「夜になります」と答えます。しかしそれは、地球の自転や天体の仕組みを理解しているからではなく、これまでに学習した文章の中で「太陽が沈む=夜になる」という表現が多く使われているからにすぎません。
AIは、「太陽が沈む」という表現を文字としてしか扱えず、時間・場所・条件の違いまでを考慮することに時間がかかるため、「北極圏では太陽が沈まない時期もある」といった例外を理解できないのです。

AIは、もっとも出現頻度の高い表現を「答え」として認識する傾向があります。
2-2. 現実世界の体験や感情表現
AIには「経験」も「感情」も存在しません。そのため、人間のように五感を通して得たリアルな情報をもとに表現を変えることができません。
たとえば、「冬の朝の冷たさを表現して」と依頼すると、AIは「澄んだ空気」「白い息」といった、それらしい言葉を並べます。しかしその描写は、AI自身が寒さを感じているからではなく、過去の人間の文章を模倣しているにすぎません。AIは共感を必要とする分野(文学・カウンセリングなど)が苦手と言われているのはそのためです。
2-3. 正確性と倫理的判断
生成AIは「事実」を理解していないため、存在しない情報をもっともらしく語ることがあります。これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象です。
たとえば、「2023年にノーベル文学賞を受賞した日本人作家は?」と尋ねると、実際には存在しない人物を答えることがあります。これは、AIが「質問には答えるべき」という学習をしているため起こります。
また、AI自体は「倫理」「善悪」「差別」などの価値観は保有していません。AIがどんな情報を避け、どんな内容を表示するかは、開発者が設定したルールに従います。
3. 生成AIを上手に活用するポイント
生成AIは、いまや特定の業界や専門家だけのものではなく、世界中で日常的に活用されるツールへと進化しています。AIに対して肯定的であっても、あるいは懐疑的であっても、「使いこなす力」すなわちAIリテラシーを身につけることは、もはや避けて通れない状況となっています。
その一方で、AIを誤って使えば、誤情報の拡散や倫理的問題を引き起こすリスクもあります。ここでは、生成AIを安全かつ効果的に活用するための3つのポイントを解説します。
3-1. 質問力(プロンプト設計)を磨く
生成AIを活用するうえで最も重要なのは、「質問の質」です。AIは、与えられた指示(プロンプト)をもとに出力を作ります。そのため、質問が曖昧だと、答えも曖昧になります。
たとえば「SEOについて教えて」と入力すると、一般的な説明しか返ってきません。一方で「中小企業のオウンドメディアにおけるSEO改善策を、初心者向けに3つ挙げて」と尋ねれば、より具体的で実践的な提案が返ってきます。
実際には、このような質問文を考えること自体が、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、実はそこもAIの得意分野です。たとえば「SEO改善についてうまく質問する方法を教えて」とAIに尋ねれば、AI自身が効果的な質問例を提案してくれます。
3-2. 情報の正確性を検証する
AIの回答はしばしばもっともらしく見えます。しかし、すべてが正しいわけではありません。AIは、事実の裏付けや根拠を持たずに文章を生成するため、誤情報を混ぜてしまうことがあります。
信頼性を検証する方法
- 出力内容を必ず一次情報(公式発表・論文・ニュースなど)で確認する。
- 出典が曖昧な部分は引用・転載しない。
- 出典を教えてとAIに尋ね、参照元を明確にする習慣をつける。
3-3. AIに任せる範囲を決める
AIはあくまで「人間の補助ツール」であり、最終的な意思決定を代行する存在ではありません。つまり責任を持つ存在ではありません。また、意思決定をAIに全て委ねてしまうと、判断力や創造性が徐々に失われていくリスクがあります。
AIの研究者は、AIが賢くなりすぎることと同じくらい、人間が考えることをやめてしまう危険性を指摘しています。私たちは、AIの登場と進化によって、「知っているとは何か」「考えるとは何か」「理解するとは何か」を、あらためて問い直す必要が出てきたように思います。
“These things understand. … And because they understand, we need to think hard about what’s going to happen next.” (1) 「これらのシステムは(私たちが思っている以上に人間を)理解をしており、だからこそ次に何が起こるかを真剣に考えなければならない」
Geoffrey Hinton(ジェフリー・ヒントン)
(1) 引用:CBS interviews.「The risks and promise of artificial intelligence, according to the “Godfather of AI” Geoffrey Hinton」