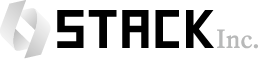「ウェブで集客したい」「SNSも活用していきたい」「広告にも挑戦してみたい」。ウェブマーケティングは企業の成長を助けるための重要な施策ですが、その際に、受け皿となるウェブサイトが整っていなければ、成果につながりにくいのが現実です。なぜなら、ウェブサイトはユーザーが最終的に信頼を判断する場所でもあり、あらゆるオンライン施策の土台と考えられているからです。
新規サイトを作るとき、あるいは既存サイトを見直すときは、単なる「デザインの刷新」や「ページ数の増加」だけでなく、施策との連動性や目的に合った導線設計、そして信頼感を伝える情報設計が重要になります。
この記事では、まず「なぜウェブサイトがウェブ施策の土台として重要なのか」を明らかにしたうえで、ウェブサイトの企画・制作・改修において押さえておきたい視点や、サイトとウェブ施策を連動させて成果を上げるための実践的なポイントを体系的にご紹介します。
1. ウェブサイト制作は目的と現状分析から始める
ウェブサイトの制作やリニューアルは、見た目を整えるだけでは終わりません。どのような目的で、どのような成果を目指すのか。そこを明確にしないまま着手すると、「とりあえず作っただけ」のサイトになってしまいます。本来ウェブサイトは、目的を達成するための手段として、ブランディング・集客・採用など、明確なゴールに向かって構築されることが一般的です。
また、現在のサイトにどんな課題があり、どこを優先的に改善すべきかを整理せずに進めてしまうと、効果の薄い改修に終わってしまう可能性もあります。
この章では、ウェブサイトを作る・直す前に必ず押さえておきたい「目的の明確化」と「現状分析」の考え方について解説します。
1-1. ウェブ制作を「なんとなく」で始めない
「とりあえずリニューアルしたい」「なんとなく今っぽくしたい」。そうした観点からウェブ制作が始まるケースは、実はかなり多いです。しかし、本来ウェブサイトは課題を解決し、成果を生み出すための手段であるというのが一般的です。ブランディング、集客、採用、資料請求など、目的次第で構成も導線もかなり違ってきます。
目的が不明確なまま制作を進めると、リリース後に「思ったほど成果が出ない」「問い合わせが来ない」といった問題に直面することも少なくありません。そのため、まずは自社がサイトに何を求めているのかを明確にすることが成果につながるウェブ制作の、最初の一歩です。
1-2. 新規サイト制作時に最初に考えるべき視点
新しくウェブサイトを立ち上げる際、「何を載せるか」よりも先に、「何のために、誰のために作るのか」を熟慮することをおすすめします。その後で、デザインやページ数、配色などの「見た目」を構成していきます。
まず重要なのは、誰に向けて何を伝えるサイトにするのか、そして訪れたユーザーにどう行動してもらいたいのかという、サイト全体を設計する視点を持つことです。認知を広げたいのか、資料請求につなげたいのか、採用エントリーを増やしたいのかによって、導線設計やコンテンツの優先度は大きく変わります。
1-3. 既存サイトのリニューアル時に課題を見える化する
効果的な改修を行うには、まず現状の課題をデータで可視化することが欠かせません。
たとえばGoogleアナリティクス(GA4)では、ページごとの閲覧数や直帰率、平均滞在時間、コンバージョン率などが確認できます。特定のページだけ離脱率が高い、滞在時間が極端に短いなどの数値から、「ユーザーが興味を失っている箇所」や「導線の分かりづらさ」などの課題が見えてきます。
また、ヒートマップツール(例:Microsoft Clarity、Hotjar、ミエルカヒートマップなど)を使えば、ユーザーがどこをクリックし、どこまでスクロールしたかが可視化できます。
CTAボタンがスルーされていたり、想定外の場所が注目されているなど、実際のユーザー行動を視覚的に把握するのに役立ちます。
1-4. ウェブサイトにおける信用の基盤
ウェブサイトは、ユーザーが企業を「信頼できるかどうか」を判断する最初の場所です。情報が不足していたり、発信内容に一貫性がないと、それだけで不安や疑念を与えてしまいます。
そこで重要になるのが、コンセプト・言葉・実績の見せ方です。たとえば、「何を誰にどう届ける会社なのか」というブランドコンセプトが明確であること、コピーや文章が信頼感を伝えるトーンで統一されていること、実績や顧客の声、第三者機関からの認証が分かりやすく掲載されていることなどが挙げられます。
プライバシーマークやISMS認証、導入実績企業のロゴ、メディア掲載実績などは、ユーザーにとって「サービスや商品を選ぶ理由」となります。また、代表メッセージやスタッフ紹介、会社の雰囲気が伝わる写真など、顔が見えるコンテンツも信頼を高める重要な要素です。
見た目や機能だけではなく、「この会社に任せて大丈夫」と思ってもらえる基盤を、情報設計の段階から整えておくことが、成果につながるサイトづくりには必要不可欠です。
2. 目的に応じたウェブ施策の設計|BtoB・店舗・EC・採用
ウェブサイトの目的は企業ごとに異なります。見込み顧客との接点を増やしたい、営業の補完として使いたい、採用活動の入口にしたい。目的によって設計や導入すべき施策も変わってきます。
難しいように思いますが、業種やビジネスモデルによって「成果につながりやすい施策」はある程度パターン化されています。適切な方向性を選ぶことで、より短期間で効果を上げることができます。
この章では、よくある4つのタイプを例に、それぞれに合ったサイト設計と施策の方向性を紹介します。
2-1. BtoB企業|信頼性重視の導線設計と資料請求導線
BtoBサイトでは「信頼される情報設計」と「導線の分かりやすさ」が成果に繋がりやすいと言われています。顧客は比較検討を前提として訪問するため、会社概要・導入事例・サービス詳細・料金の明確さが重要です。
また、いきなり問い合わせよりもホワイトペーパーのダウンロードや資料請求など、ハードルの低いアクションを用意することで、リード獲得につなげやすくなります。
2-2. 店舗ビジネス|InstagramとGoogleマップ連携を軸に
飲食店・美容室・整体院などの店舗型ビジネスでは、「検索やSNSで見つけてもらう→来店につなげる」までの流れが重要です。 Googleビジネスプロフィールとの連携、MEO(ローカルSEO)対策、SNSの投稿連携などをセットで整備することで、地図検索からの流入とSNS流入の両面をカバーできます。
Instagramの投稿を埋め込んだり、アクセス・予約ボタンを視認性高く設置するなど、「来店までの障壁をなくす設計」が鍵となります。
2-3. ECサイト|商品ページ改善と購入フローの最適化
ECサイトでは、サイト自体が「販売スタッフ」の役割を担います。そのため、商品情報の質や購入のしやすさが売上に繋がりやすいです。商品検索・カテゴリ分け・比較機能・レビュー表示などを充実させることで、ユーザーの検討をスムーズにし、「迷わせない導線」が成約率を高めるポイントになります。
加えて、カートの使いやすさや、スマホでの表示・操作性など、購入完了までのユーザー体験も重視する必要があります。
2-4. 採用特化サイト|求人ページ導線と社員紹介コンテンツ
採用目的のサイトでは、「働く人の雰囲気」「社風」「価値観の一致」を伝えるコンテンツが重視されます。求人一覧だけでなく、社員インタビュー・一日のスケジュール・福利厚生・代表メッセージなどを掲載し、共感を得られる設計が効果的です。
エントリーフォームへの導線も重要で、「エントリーする理由」が伝わる設計と、「エントリーのハードルを下げる」工夫が成果に直結します。
3. 新規制作時に組み込むべきマーケティング施策
ウェブサイトは公開してから集客や運用を考えるのではなく、新規サイト制作の段階からマーケティング活動と連動する設計をしておくことで、公開後すぐに効果を出しやすくなります。特に、CV(コンバージョン)導線の設計や、SNS・広告・SEOとの連携、効果測定の仕組み作りなどは、あとから手を加えるよりも、最初に仕込んでおく方が効率的です。
この章では、サイト制作初期に組み込んでおきたい5つのマーケティング視点をご紹介します。
3-1. 最初に設計すべきウェブサイトのCV導線
集客がうまくいっていても、サイト内に「行動の着地点」が設計されていなければ、なかなか成果には結びつきません。問い合わせや資料請求、予約などのCV(コンバージョン)ポイントをあらかじめ明確にしておくことが大切です。
CTA(コールトゥアクション)の配置やボタンの見せ方、フォームの入力項目の整理など、細かな部分を丁寧に設計しておくことで、ユーザーの行動を自然に後押しすることができます。
こうした工夫が、ウェブサイトを“成果につながりやすい状態”へと近づけてくれます。
3-2. 目的別にLPを仕込んでおく
ユーザーの行動を促すために、目的ごとに最適化されたLP(ランディングページ)の存在はかなり大きいです。キャンペーン告知・商品紹介・採用特設など、ページごとに訴求内容や導線設計を変えることで、成果率が大きく変わります。
特に広告やSNSからの流入を想定する場合、一般的なページよりも「目的特化型のLP」を用意する方が、ユーザーの離脱を防ぎ、CVにつなげやすくなります。
3-3. SNSマーケティングと連携するサイト設計
SNSマーケティングは認知や共感を広げ、ブランドへの信頼やファンを育てていくために有効な施策です。 Instagramなどでの投稿を通じてユーザーとの関係性を深めていくためには、その効果を最大化できるよう、ウェブサイト側の設計もあらかじめ整えておくことが大切です。
たとえば、SNS投稿を埋め込むスペースを用意したり、プロフィールリンクから直接アクセスされることを想定して専用ページを設けておくことで、SNSから流入したユーザーとのタッチポイントがスムーズになります。
また、LINE公式アカウントへの導線や、SNSキャンペーン情報を反映した特設ページを準備しておくと、SNS施策とウェブサイトが一体となった動線設計が可能になります。
SNSとウェブサイトは切り離して考えるのではなく、ブランディングや顧客接点の一貫性を持たせるという視点で連携設計を進めていくことが、成果につながる鍵になります。
3-4. 初期から仕込むSEO視点
SEOはサイト公開後に徐々に取り組むというのが一般的です。なぜなら、SEOは長期的に安定した集客を実現するための土台となる施策で、即効性があまりないからです。しかし、時間をかけて効果が出る施策だからこそ、初期段階から取り組むことが効率的という考え方もあります。
ターゲットキーワードの設定、タイトル・ディスクリプションの整備、Hタグの適切な配置、内部リンク構造の最適化など、基本的なSEO要素は制作時に組み込んでおくことで、検索エンジンに評価されやすい構造を作ることができます。
また、コンテンツマーケティングなどを展開する予定がある場合は、ブログやコラムの更新スペース、カテゴリー構造をはじめから設計しておくことで、未来の施策の展開がスムーズになります。
3-5. ウェブ広告を見越した計測と最適化の準備
ウェブ広告は「広告を配信して終わり」ではなく、その成果をしっかり計測し、改善につなげられる体制を整えておくことが重要です。そのためには、サイト制作段階で Googleアナリティクス(GA4)やGoogleタグマネージャー(GTM)などの計測ツールを導入しておくことが重要です。
また、広告流入ごとの効果測定や、A/Bテスト(バナー・導線・コピーの検証)を行う場合は、柔軟に調整できる構造や設計の余白も必要です。広告効果を最大化するには、「広告を出せば効果が出る」という考え方ではなく、「広告施策に耐えうるサイトの土台を整えておくことが、成果を左右する重要なポイントになります。
4. 改修・リニューアル時に検討するポイント
既存のウェブサイトを活かしながら成果を高めていくためには、「どこを、なぜ、どう改善するのか」を明確にしたリニューアル計画が欠かせません。せっかくリニューアルしたサイトが、ユーザーに「あれ?別のサイトに来てしまった?」などの戸惑いを与えてしまったり、操作性がかえって悪くなってしまうこともあります。
この章では、ウェブサイトの改修・リニューアルを行う際に押さえておきたい施策と視点を紹介します。現状の課題を数値で把握し、構造やコンテンツ、表示パフォーマンスまで総合的に見直していくことで、成果に直結する改修が可能になります。
4-1. サイトマップの見直しと動線設計
リニューアルでは、見た目だけでなく「構造の整理」が重要です。情報の重複や階層の深さ、回遊性の低さなどは、ユーザー体験を損ねる要因になります。まずは現状のサイトマップを洗い出し、重要なページが適切な場所に配置されているか、ゴール(CV)までの動線がスムーズかを確認しましょう。必要に応じてカテゴリやグローバルナビゲーションを整理することで、訪問者のストレスを軽減し、目的ページへの到達率を高めることができます。
4-2. 改善ポイントが見えるアクセス解析
「なんとなく」ではなく、データに基づいたリニューアルを行うために、Googleアナリティクス(GA4)やヒートマップの活用が不可欠です。
たとえば、離脱率が高いページや直帰率の高い流入元、スクロール率の低いコンテンツなどを把握することで、どの要素がボトルネックになっているのかが見えてきます。
特にヒートマップでは、CTAボタンが注目されていない、想定と異なるエリアがクリックされているといった“行動のズレ”を視覚的に確認できるため、改善箇所の判断がしやすくなります。
4-3. 表示速度やモバイル対応の最適化
ユーザー体験を損ねる代表的な要因が「表示速度」と「モバイル最適化」です。特にスマホユーザーの比率が高い現在、これらの改善は避けて通れません。
PageSpeed Insights や Lighthouse などのツールで診断し、画像の軽量化、キャッシュ活用、不要なスクリプトの削除などを行うことで表示速度を改善しましょう。
また、モバイルでのフォントサイズ、ボタン配置、スクロール距離など、使いやすさを意識した設計に見直すことで、離脱率の改善につながります。
4-4. SEOリライトとコンテンツ資産の活用
検索流入を強化するには、既存コンテンツの見直し(リライト)と、新たなキーワードへの対応が効果的です。特に、検索順位が中位(11〜30位)に位置するページは、少しのリライトで順位上昇が狙える伸びしろを持っていたりします。
また、過去のブログ記事や実績紹介、よくある質問などを整理し、内部リンクで有機的につなげることで、サイト全体の評価を高めることができます。新規作成だけでなく、既存の資産を活かすことにも十二分の価値があります。
5. 効果測定と継続的改善で成果を伸ばす
ウェブサイトは公開後の活用と育成が重要なポイントです。訪問者の行動を可視化し、どのコンテンツが成果に貢献しているのかを分析することで、次の一手となる改善策が見えてきます。
この章では、日々の運用の中で成果を最大化するための効果測定の方法と、継続的な改善に向けた視点をご紹介します。
5-1. オンライン施策の主な指標と見方
効果測定の第一歩は、何をもって成果とするかの指標を明確にすることです。代表的な指標には、以下のようなものがあります。
- インプレッション数・クリック率(CTR):広告や検索結果での露出と反応率
- CV数・CV率:問い合わせ・資料請求・購入・エントリーなどの成果数とその率
- 直帰率・離脱率:どこで離脱されたか、どのページで離脱が多いか
- 平均セッション時間・ページ遷移数:ユーザーがどれくらいサイトを閲覧してくれているかの指標
これらをGA4やヒートマップツールなどを使って定期的に確認することで、サイトのどの部分が機能しており、どこに改善余地があるかを把握できます。
5-2. オフライン成果とのつなぎ方
最終的な行動がオフラインで完結するビジネスにおいては、ウェブ上でのデータだけでなく、実際の売上や来店などのリアルな成果とどう結びついているかを見極めることも重要です。たとえば、電話での問い合わせが多い業種では、Googleビジネスプロフィールの「電話タップ数」や、サイトに掲載した電話番号への発信件数を計測対象に含めるとよいでしょう。
また、店舗ビジネスであれば、クーポンの利用状況や「ウェブを見た」と伝えてきた来店客数を記録するなど、オフラインとオンラインをつなぐ簡易的なKPI設計も効果的です。
5-3. 継続的な改善につなげる運用視点
効果測定は、一度きりではなく継続的に行うことで、より信頼性の高いデータとなり、施策の価値を高めてくれます。たとえば、「問い合わせフォームまで到達する人が少ない」と初期段階で分かったとしても、測定を続けるうちに「実はフォーム直前の説明に原因がある」「ターゲットがそもそも違っていた」など、別の課題が浮かび上がってくることもあります。
このように、データから課題を仮説立てし、ページ改修や文言変更などの対策を講じ、再度検証していくというPDCAサイクルを地道に回していくことが、ウェブサイトの成果を積み重ねていく鍵になります。加えて、Googleサーチコンソールなどを活用し、検索パフォーマンスの変化を追うことで、SEO面での継続的な改善にもつなげられます。
Googleサーチコンソールなどで検索パフォーマンスの変化を確認しながら、SEO面の改善も継続的に行うことで、中長期的な集客力の底上げにもつながります。
まとめ|成果を生むウェブ戦略には強固なサイト設計が必要
ウェブサイトはすべてのオンライン施策が帰着する戦略の土台です。どれだけSNSや広告を活用しても、最終的にユーザーが判断を下すのは、企業の顔ともいえるウェブサイトの内容と設計にほかなりません。
この記事では、目的設定や導線設計、各業種に適した施策の組み込み方、そしてサイト公開後の継続的な改善手法までをご紹介しました。これらを新規制作時やリニューアル時から意識的に設計することで、サイトは情報掲載の場から成果を生むマーケティング資産へと進化します。
変化の早いデジタル環境において、成果を継続的に上げていくには、最初の設計と運用の改善という両輪を回し続けることが不可欠です。自社サイトを「戦略の起点」として見直し、より強固なウェブマーケティング体制を築いていきましょう。