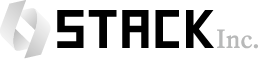検索エンジンの進化によって、ユーザーが情報を取得する方法は大きく変わり始めています。これまでの検索は「クリックしてサイトへ移動し、答えを得る」ことでした。
しかし現在は、検索結果を開かなくても、検索画面だけで必要な情報がわかってしまうことが増えています。こうしたゼロクリック検索の広がりによって、従来のSEOの考え方も見直しが必要になっています。
さらにGoogleは、生成AIによる回答を検索結果に組み込むSGEを展開し始め、ユーザーの検索体験は新しいフェーズへと移行しています。この変化に対応するため、今注目されているのがSXOです。
本記事では、従来の検索の種類からゼロクリック検索、そしてSGE・SXOまでを体系的に解説し、これからのSEO担当者が押さえるべきポイントを分かりやすくまとめます。
1. 従来型検索の3種類
この章では、従来から存在するクリックして情報を得ることを前提とした3つの検索方式を整理します。これを押さえることで、ゼロクリック検索の変化点がより理解しやすくなります。
1-1. オーガニック検索
オーガニック検索とは、検索エンジンの自然検索枠に表示される結果です。広告を含まない純粋な検索結果であり、SEO施策がもっとも反映される領域です。
オーガニック検索の特徴
- 自然検索からの流入が中心
- クリック率(CTR)や滞在時間などが指標
- どのサイトが良いかをユーザー自身が選択
SEOでは最も基本となる検索方式です。
1-2. パーソナライズド検索
パーソナライズド検索は、ユーザーの履歴・興味・位置情報などに基づいて結果が最適化される検索です。
パーソナライズド検索の特徴
- 一人ひとりに異なる検索結果が表示される
- ローカル検索(例:近くの店舗)が強く影響
- Googleログイン環境で結果が変わりやすい
SEO担当者にとっては「順位が固定されない」という難しさがあります。
1-3. シークレットモード検索
シークレットモードでは、検索履歴やログイン情報を反映しない検索結果が表示されます。
シークレットモード検索の特徴
- 平均的に近い検索結果が見られる
- SEOの調査用途として一般的
- 位置情報は一部影響する
SEO調査時に最もよく使われる検索方式です。
2. ゼロクリック検索とは何か
近年増えているのが、検索結果をクリックせずに検索画面上で答えを得るゼロクリック検索です。
企業サイトの表示機会が減る可能性があるため、SEO担当者にとって非常に重要なテーマです。
2-1. ゼロクリック検索
ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果をクリックせず、検索画面で答えを完結させる検索行動のことです。
「ゼロクリック検索とは、検索画面そのものに回答が表示され、どのサイトにもアクセスせずに完結する検索行動のことです。」
— Jeff Hirz(OuterBox Design)「Zero-Click Search Results for SEO」より引用
ゼロクリック検索の代表例
- 天気予報
- 地図情報
- 計算式
- ナレッジパネル(有名人情報など)
- 強調スニペット(Featured Snippet)
情報の多くが検索画面(SERP)上で完結するため、サイト訪問の機会が減るという課題があります。
2-2. ゼロクリック検索への対応策
1. 検索意図が深いキーワードへのシフト
概要・定義系(ノウクエリ)はゼロクリック化しやすいため、比較・選び方・判断・注意点など深い意図のキーワードを狙う。
2. リッチリザルト対応
- FAQ構造化データ
- パンくずリスト
- How-to(手順)構造化データ
検索画面上で目立つことで、クリック率を維持できます。
3. ブランド名検索の強化
ゼロクリック検索が進んでも、指名検索は必ずクリックされるため、ブランド力を高める施策が有効です。
ゼロクリック検索が進むほど、検索結果だけでは伝えきれない価値や、サイトに来る意味 をしっかり作ることが重要になります。ウェブ戦略全体を見直したい方は、以下の記事も参考になります。
🔗 ウェブサイトはウェブ戦略の土台!サイトの重要性と並行して行いたいウェブ施策を解説
2-3. ゼロクリック検索が増えた背景
ゼロクリック検索が増加した理由は主に以下の3つです。
- Googleが検索結果に多くの情報を表示するようになった
→ 強調スニペット・知識パネルの増加 - スマホでの検索が主流になった
→ ユーザーは早く答えを知りたい - 生成AIの発展による要約回答の増加
→ SGE登場で検索画面が回答提供の場になりつつある
3. SGEとSXO、そしてSEOの違い
ゼロクリック化と生成AIの影響により、「検索すれば必ずクリックされる」という前提は崩れつつあります。これからのSEO担当者は、SGEとSXOの理解が欠かせません。
3-1. SGEとは?
SGE(Search Generative Experience)は、Googleの検索結果に生成AIが回答要約を表示する仕組みです。
SGEの特徴
- 検索結果の一番上にAI要約が表示される
- 複数サイトの内容をAIが統合して回答
- 質問を続けられる対話型インターフェース
サイトへ遷移する前に答えが完結するため、ゼロクリックがさらに増えると考えられます。
3-2. SXOとは?
SXO(Search Experience Optimization)は、SEOのように検索エンジン向け最適化ではなく、
ユーザーの検索体験そのものを最適化するという考え方です。
SXOが重視する要素
- 情報へたどり着くまでのストレスが少ない
- 読みやすい・探しやすい・迷わない
- CTAが自然で押しやすい
- 不安を事前に解消できている
生成AIとゼロクリックの時代では、サイトに来る意味を作る体験価値が重要になります。
3-3. SEOとの違い
| 概念 | 目的 | 役割 |
|---|---|---|
| SEO | 上位表示/流入増加 | 検索エンジン向け |
| SGE | 検索画面で回答提供 | AIが自動要約 |
| SXO | 体験の最適化 | ユーザー向け |
SEO(Search Engine Optimization)だけを強化しても、ゼロクリックやSGEの時代には不十分です。
流入してもらうためには、SXOによる体験価値が不可欠になります。
まとめ|「検索体験の最適化」が鍵
ゼロクリック検索やSGEの登場により、検索は「サイトへ誘導する装置」ではなくなりつつあります。
SEO担当者が今後重視すべきポイントは次の3つです。
- 検索画面で完結しない深い検索意図のキーワードを狙う
- リッチリザルトで検索画面上の存在感を高める
- SXOを意識し、訪問後の体験を最適化する
検索体験が高度化するなかで、SEOの役割は「順位を上げること」から、
ユーザーに価値ある体験を提供することへと進化しています。